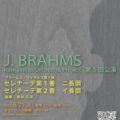「死を生として演じる」という宿命に抗して:笑うドン・ジョヴァンニ
文=小島広之
ドン・ジョヴァンニは女たちを物色する。その欲望を邪魔するものがあれば、ためらうことなく騙し、殴打し、破壊する。殺人も厭わない。ドンナ・アンナを我がものにするために、その父・騎士長をサーベルで突き殺し、結婚式会場にあらわれれば新郎マゼットを一蹴して新婦ヅェルリーナを誘惑する。それにもかかわらず、彼が単なる悪と映らないのはなぜだろうか。それは彼の蛮行がオペラを駆動させる原動力となっているからである。機械のように蛮行を強いられるドン・ジョヴァンニ——悪行を積み重ねた男は、まるで怨嗟のベルトコンベアに乗せられるようにしてフィナーレまで運ばれる。ドン・ジョヴァンニはオペラに仕える。なるほど愛に満ちた男であるが、その愛は全く瑞々しくない。
ドン・ジョヴァンニにかぎったことではない。長さにして四方10メートル程度、時間にして3時間程度、「オペラ」という閉ざされた箱庭に押し込められた登場人物たちは、あくまで機械的に律動する。そうしないかぎり、この箱庭ではドラマが進行しないからだ。それゆえにオペラという芸術は二重の意味で「死」を運命づけられている。つまり、登場人物たちはドラマの奴隷として生を失っており、「作品」もまた何千回と繰り返し上演されることで生を擦り減らしているのだ。その一方で、今日のわたしたちが接する芸術の登場人物たちは、なんと生き生きとしているだろう。浩瀚な小説、ロングランのテレビドラマ、重厚なテレビゲーム——そこでわたしたちは、緻密な人物描写と新鮮な筋立てを通じて、血の通った人間と出会うことができる。この比較において、オペラは「貧しい」芸術であると言わざるを得ない。だが、まさにその「貧しさ」に、オペラの可能性が潜んでいるのだ。
オペラの真価は、この「死」を「生」として舞台にかけざるを得ない点にある。いくら登場人物たちが「死んで」いようとも、舞台の上では、彼らは生きた人間として振る舞わなければならない。それゆえこの芸術では演出が重要になるのだ。
この生と死のあわいをHamamoto Opera Projectはいかに扱ったのか。舞台装置はシンプルであった。階段と踊り場が設置されており、役者の立体的な動きを演出しやすいつくりになっていた。背景には、登場人物たちの心情を映し取るように緑や赤色に色を変えるスクリーンが設置された。天井からは格子状のオブジェがいくつか吊り下げられていた。衣装は伝統的であり、モーツァルト時代の再現を試みているように見えた。近年では、特に『ドン・ジョヴァンニ』のような「名作オペラ」を上演する場合、作曲家の意図を大胆に読み替え、しばしば物議を醸すような改変を舞台装置や衣装において行うことも少なくない。それに対してHamamoto Opera Projectは、上述のようにある種の保守性を徹底していた。彼らは、そのような大胆な演出によって作品に人工的な「生」を注ぎ込むのではなく、むしろ作品の死にあえて無抵抗で向き合い、それをそのまま舞台に現前させることを狙ったようにみえた。もちろん、広範な観客層への訴求を考慮して、保守的な演出に踏み切らざるを得なかったという事情もあっただろう。しかし、素朴さを是としていようとも、平凡に陥ることを是としたわけではない。その鍵となるのが、自然主義的に振る舞う役者たちの中で際立っていたドン・ジョヴァンニの「笑み」であった。Hamamoto Opera Projectのドン・ジョヴァンニは、要所で印象的に笑う。「笑み」は素朴な舞台においても全体の調和を乱すことはない、自然な行為として成立していた。加えて笑いは、本来ならば、生き生きとした人間を特徴づける行為でもある。しかしHamamoto Opera Projectのドン・ジョヴァンニは、たとえば蛮行を行うときや、自身が窮地に陥ったときにさえ笑う。結果として、彼の非人間性、仮面劇的なそっけなさが印象付けられた。その笑みは、彼の「死」に瀕した硬直をむしろ逆説的に強調する装置となっていたのだ。徹底的に「オペラ」の登場人物であるドン・ジョヴァンニ。そんな彼が2024年11月17日という時代に、川崎市民プラザふるさと劇場という場所に生を与えられるという不自然さ。このことが生の舞台の上で強調され、生と死のせめぎ合いが絶妙な塩梅で可視化されたのだ。Hamamoto Opera Projectの『ドン・ジョヴァンニ』は、奇を衒った刷新とは異なる形で、オペラという芸術の本質——「死を生として演じる」という宿命——をわたしたちに突きつけるものであった。
また、本公演の会場は300席程度の劇場であったが、それにもかかわらずピアノ伴奏ではなくオーケストラによる上演がなされた点も特筆すべきであろう。この試みが、「死と生」のコントラストを鮮明に演出するための土台となっていたことは見逃せない。
小島広之(こじま・ひろゆき)
愛知県出身。慶應義塾大学理工学部化学科を経て同大学文学部美術美学史学専攻を卒業。東京大学大学院総合文化研究科超域文化科学専攻表象文化論コース博士前期課程を2020年に修了。ベルリン・フンボルト大学大学院音楽学メディア学研究所を経て、現在、東京大学大学院総合文化研究科超域文化科学専攻表象文化論コース博士後期課程に在籍中。日本音楽学会、美学会、表象文化論学会、Gesellschaft für Musikforschung所属。
主な論文に「パウル・ベッカーの客観主義的な音楽美学」(『音楽学』2022年)、「ハンスリック『音楽美について』における純粋音楽作曲論:主観と客観の二重性」(『美学』2024年)がある。2022年に論考「『新しさ』の分析論:現代音楽における差異、価値づけ、そして魅力」で第9回柴田南雄音楽評論賞奨励賞を受賞。
また、2021年には「スタイル&アイデア:作曲考」を立ち上げ、現代の作曲家による作曲論を周知している。