オペラではキャスト、合唱団は舞台上で歌うだけではなく、演技もします。 演技をつけていく「立ち稽古」の現場では、 どのような流れで、何に意識をして稽古を進めているのかを演出家に聞きました。

立ち稽古は演技を組み立てる稽古です。単に場面を成立させるのが目的ではありません。テキストと音楽を最大限に活かし、活かされる演技を構築する必要があります。それには、多くの段階を経る必要があります。
まずは歌詞の解釈です。単語レベルでの重みづけや、発言の意図を吟味することにより、一つの台詞が様々なニュアンスを帯びます。これらを組み合わせることで、会話の熱量や場面の緊張感が大きく変化し、テキストの意味合いが豊かになっていきます。

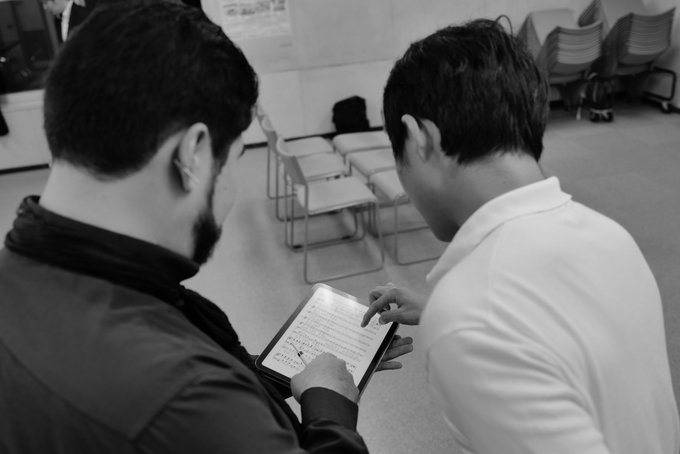
この作業を通じて、演者の各々がキャラクターの理解を深めます。 オペラでは音楽が進めば自ずと次の歌を歌えますが、実際は発言には動機が存在し、沈黙にすら理由が必要です。自分が何者なのかを、典型的な人物説明だけではなく、楽譜の細部から拾い上げます。
実際に体を動かす時には、音楽の流れや間を感じながら、最適な動きを模索します。演劇と異なり、オペラでは楽譜の中に、会話の尺や言葉の強弱がある程度示されています。音楽をよく聞くことで自分の解釈を問い直し、旋律と心の平仄を合わせることが求められます。


また、重唱では素早い掛け合いや、逆に相手の歌を聞く長い待ち時間が生じる場合もあります。なぜそこに割って入るのか、あるいは何を思って聞いているのかを明確にし、自然なリズムの中に自分たちがいるように場面を作り上げます。
皆で演技について話し合い、演出が固まっていく中で、それぞれが自分の役を越え、互いのキャラクターについて理解していきます。 全ての幕においてこれを積み重ねることで、それぞれの場面の意義、そしてオペラ全体の志向するところが共有されていきます。



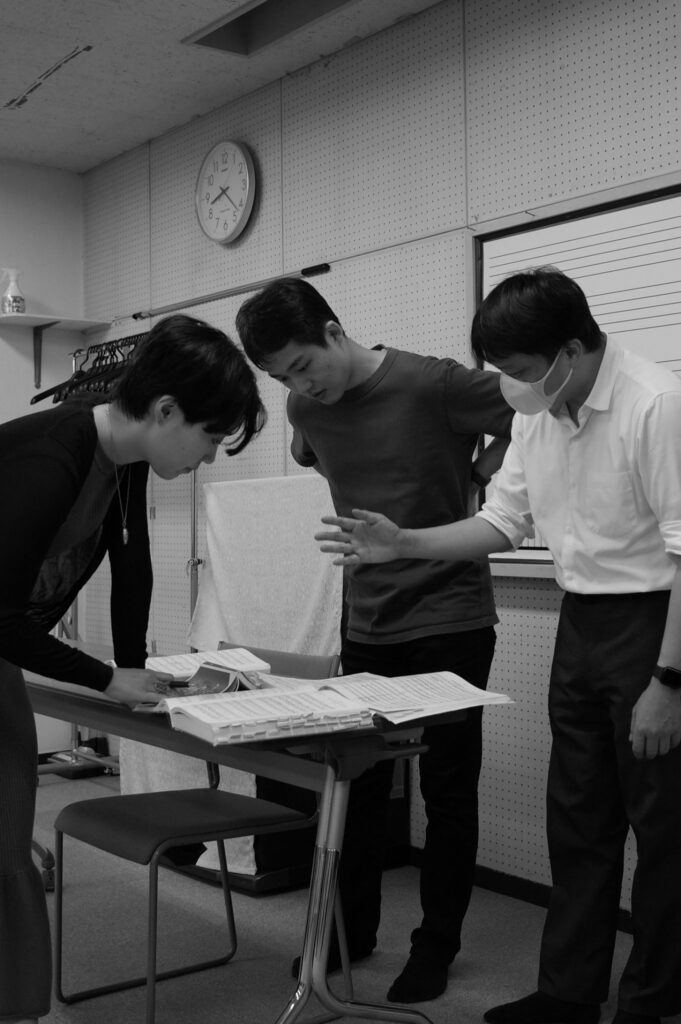
こうした共通理解をもとに、改めて一つ一つの芝居に立ち戻ることで、自然な演技が発露します。また、相手の人格と行動を熟知することで、最適な応答を返すことができます。テキスト、音楽、演技の全てが一致した、自発的であり迷いのない状態が、立ち稽古の最終目標です。(文:伊藤 薫)


